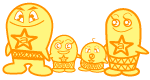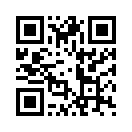2007年06月21日
待っている時間の長さは、つまり悟るための長さだ
待っている時間の長さは、つまり悟るための長さだ。待っている先に待ち受けている現実があることを悟るため、人は待つという時間に身を浸す。
だから今、不思議なことに僕は予想以上に平然としていられるのかもしれない。 (辻 仁成「冷静と情熱のあいだ Blu」より)
待つことができるということは、信じることができるということです。
信じることができるということは、恐がる必要がないということです。
恐がる必要がないということは、待つ事ができるということです。
あらゆることには、やはりあらゆる問題がつきまとってきます。
その問題が解けずについ焦ってしまい、どうしようもなく混乱してしまいます。
天才ならば、頭を空っぽにしてしまうことで、心に何かが入り込む余地みたいなものを消し去り、ただ目的のために能力を発揮していくことができるかもしれないけど、僕の場合は問題を忘れようと一所懸命別のことを考えて、消し忘れたガスコンロのように心を不安の中で焦がしてしまう。
でも、不安は不安としてその存在を認めないことには、物事は解決できません。
そして朝を待ち、晴れるのを待ち、恋人の電話を待ち、就業時間を待ち、給料日を待ち…その先に一瞬だけ輝く結果がある。後で考えれば「な~んだ、結局そういうことだったのか」と拍子抜けしたような単純な答えしか待っていなかったとしても、やっぱりその答えを得るためにはそれだけの時間が必要だったのです。
たぶん、僕達は何かを失うことよりも、何かを得て責任を負わされることを恐れている。
不安のない人生を送れたらと思う…でも、楽しいこと、嬉しいことは、不安がなければ相対するものがなくなる…争いのない国では、“平和”であるということがどんなことか理解できないように。
<果報は“練って”待て> 本田宗一郎
大切なことは、自分が不安からいかに遠い場所へ行けるのかを考えるのではなく、どれだけ不安に近いところでへっちゃらな気持ちで構えていられるかを“挑む”か…それが“待つ”。アインシュタインの相対性理論(※)のように時間は心によって質量を変えます。
何物も怖れない精神状態なんて天才じゃないとなれないかもしれないけど、最後は“信じるに足る自分”でいられるかどうかという問題になると思います。そこにはただ、事実を事実として“受け入れる”覚悟があります。
「待つ」行為は太平洋のど真ん中で地震が起こることに似ています。
一箇所で震えれば、世界の他の端まで響くからです。それまでにかかる時間が「待つ」。
僕達は無意味に時間を浪費しているように思いながら、物事は絶えず流れながら触れ合っているのです。笑顔は波になり、いつか誰かの心の岸に届くでしょう。 信じようと待ち、結果を信じるしかない。
待っている未来は、良い夢かもしれないし悪い現実かもしれない。どちらにせよ、「待つ」ことは、今まで見えていなかった新しい現実へ自己を「解き放つ」ことになるようです。
(※) アインシュタインの相対性理論。
「動くものは、止まっているものよりも時間の進み方が遅くなる」
「動くものは、進行方向の長さが縮む」
「動くものは、質量(重さ)が増える」
よく聞くのが「ウラシマ現象」と言うもので、光の速度(約秒速30万km)で宇宙に一年旅行して地球に帰ってくると、地球では2~3年の時間が経っていることがあるそうです。
それは時間が空間と質量によって進み方が変化するという証明です。 また意識の中で感じる「時間」は測定できないのです。
総量としての時間は変わらなくても、楽しい時間は早く過ぎ、嫌な時間は永遠とも思えるような、“相対的”に人によって時間の進み方は変わるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このカテゴリーの記事一覧⇒ 時間に関する名言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ブログランキングに参加しています。クリックで応援していただけると励みになります。

Posted by ayanpa at 10:33│Comments(0)
│時間に関する名言
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。