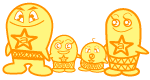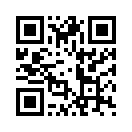2006年08月11日
完璧な絶望と喪失感
「完璧な文章などといったものは存在しない。
完璧な絶望が存在しないようにね。」
(村上春樹「風の歌を聴け」)
つまり、「完璧な人生を歩みたければ、完璧な絶望が必要」なのです。私の解釈は「完璧な人生とは、“孤独”である」です。誰にも侵されることのない本来の自分へ回帰し、かつ社会を普遍的価値で創造する生き方…それが“孤独”。深い喪失感の穴から沸き出る泉のような肯定性。
ある瞬間に深い井戸の中に落ち、閉じ込められて誰も自分のことを知る存在がいなくなった。
「誰も自分のことを知らない」ということは、「自分は存在しない」ということ。
だから、どれだけ素敵な名前があったとしても、その名を呼ばれることはないのです。
でも、その自分が存在しない場所のはずなのに「自分が生きている」という“事実”だけがある。
生きていること、生きていくこと…、多くの時間は自己から多くのものを失わせ、それはもう二度と取り戻すことのできないこと。だから、満開の桜の花がはかなく散るように、絶望という最後の諦めが、肯定性をもって世界を創りあげているという“事実”がこの言葉の中にあると思うのです。
「強い人間なんてどこにも居やしない。
強い振りのできる人間が居るだけさ。」
誰もが同じです。ただ誰よりも早く、人間が“弱い”という事実を知ってしまったとしたら、それを知らない人の手前見せるわけにはいかず、“強い振り”をしてでも生きていかなければならないのです。
そのためには、誰とも同じでない自分なりの世界観を持つ事が必要となってくるのです。
ただ単に生きる事だけを営むのであれば、本能に任せて繁殖し新しい種ができたらすぐに死んでいけばいい。でも、そうじゃないから「理性」や「個性」を持って色々な表現方法が人間には用意されているのです。
「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る。」
(高村光太郎)
だから、人は何かのために生きるというのではなく、“生きるから何かのためになる”のです。
「神は死んだ。」
(ニーチェ)
「自由」というと、束縛や制限がない状態をさし、何かから開放されるかのような感覚があります。
でも、誰の導きもなく、自分の頭で考え、自分の真理を追いかければ、そこに絶対者である“神”の役割がなくなってしまい、ガリレオやダーウィンの科学的解明は、まさに“神の御業”に反する無神論的実存主義の“自由”になります。
また別で、“神”という支配者がいないのなら、好き勝手に生きればいいと、ヒッピー族などの間でこの考え方はセックスと薬と暴力の“快楽主義”…何をしても自由だと勘違いされ、現代にも影響を及ぼし、その結果として“自分の存在の理由”がわからなくなった人が自殺や無差別殺人を犯している現状があります。それは花が咲く理由を失い、つぼみのまま枯れ落ちるようなものです。
「絶えず実存で在り続ける人間は、
絶えず行動の選択を強いられる。」
(サルトル)
実際人間は「何かから自由になる」のではなく、「もともと自由である以外に選択の余地は与えられていない」のです。例えば、目の前に紙と鉛筆を出されて“自由にすればいい”と言われたらどうするか。私達はその紙と鉛筆をどうしようとも“自由”なのです。描いても描かなくても、破っても、折っても、捨てても、無視しても“自由”です。(ここで言う“紙”と”鉛筆“を、“生命”と“人生”に置き換えてみて下さい。)
そう、“自由”とは、全てのことを自分で選択していかなければならないという束縛…“不自由”なのです。だから、「何かをしなければ、何にもなれない」という不自由を常に背負って人間は生きているのです。
頭がよくても使わなければ、お金持ちだったとしても、堕落し何もしなければ何も充実しないのですし、カルト宗教やインチキ占いにのめり込んでしまう人は、権威に依存すれば責任の所在は自分以外になるので安心だと、自己放棄・「誰かに自分の人生を決めてほしい」という選択をしているのです。だから、不幸になりたいと思っても、不幸になる行動を“選択”しなければなりません。
大切なことは、どれだけ虐(しいた)げられた状態に貶(おとし)められたとしても、心がそれにどう応えるか? 自分で選択をしていくことを恐れないこと。その人の一瞬一瞬の行動そのものが、その人の価値観や人間性を自ら決定していきます。つまり、絶望の深淵(しんえん)にたたずんでそれを認めてしまえば、不自由であることを肯定できるのです。生きなければ、死ぬことができない…「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」のです。死んだように生きている人間が、絶望や死ぬことを考えるはずがないのです。
人間は死に向かって生きている…そのどうしようもない喪失感…どうしようもない絶望は、最後に肯定性を持って“孤独”というカタチで社会という鏡に映すようです。
参:孤独とは、閉ざされたものではなく、むしろ社会的広がりのある生き方だ 岡本太郎
「地獄変の屏風(びょうぶ)を描こうとすれば、地獄を見なければなるまいな」 芥川龍之介「地獄変」
一つの能力を獲得するという歓びは、別のある能力を喪失するという哀しみ 茂木健一郎
運というものは、自分をどこに“運ぶ”のか?ということだ。
完璧な絶望が存在しないようにね。」
(村上春樹「風の歌を聴け」)
つまり、「完璧な人生を歩みたければ、完璧な絶望が必要」なのです。私の解釈は「完璧な人生とは、“孤独”である」です。誰にも侵されることのない本来の自分へ回帰し、かつ社会を普遍的価値で創造する生き方…それが“孤独”。深い喪失感の穴から沸き出る泉のような肯定性。
ある瞬間に深い井戸の中に落ち、閉じ込められて誰も自分のことを知る存在がいなくなった。
「誰も自分のことを知らない」ということは、「自分は存在しない」ということ。
だから、どれだけ素敵な名前があったとしても、その名を呼ばれることはないのです。
でも、その自分が存在しない場所のはずなのに「自分が生きている」という“事実”だけがある。
生きていること、生きていくこと…、多くの時間は自己から多くのものを失わせ、それはもう二度と取り戻すことのできないこと。だから、満開の桜の花がはかなく散るように、絶望という最後の諦めが、肯定性をもって世界を創りあげているという“事実”がこの言葉の中にあると思うのです。
「強い人間なんてどこにも居やしない。
強い振りのできる人間が居るだけさ。」
誰もが同じです。ただ誰よりも早く、人間が“弱い”という事実を知ってしまったとしたら、それを知らない人の手前見せるわけにはいかず、“強い振り”をしてでも生きていかなければならないのです。
そのためには、誰とも同じでない自分なりの世界観を持つ事が必要となってくるのです。
ただ単に生きる事だけを営むのであれば、本能に任せて繁殖し新しい種ができたらすぐに死んでいけばいい。でも、そうじゃないから「理性」や「個性」を持って色々な表現方法が人間には用意されているのです。
「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る。」
(高村光太郎)
だから、人は何かのために生きるというのではなく、“生きるから何かのためになる”のです。
「神は死んだ。」
(ニーチェ)
「自由」というと、束縛や制限がない状態をさし、何かから開放されるかのような感覚があります。
でも、誰の導きもなく、自分の頭で考え、自分の真理を追いかければ、そこに絶対者である“神”の役割がなくなってしまい、ガリレオやダーウィンの科学的解明は、まさに“神の御業”に反する無神論的実存主義の“自由”になります。
また別で、“神”という支配者がいないのなら、好き勝手に生きればいいと、ヒッピー族などの間でこの考え方はセックスと薬と暴力の“快楽主義”…何をしても自由だと勘違いされ、現代にも影響を及ぼし、その結果として“自分の存在の理由”がわからなくなった人が自殺や無差別殺人を犯している現状があります。それは花が咲く理由を失い、つぼみのまま枯れ落ちるようなものです。
「絶えず実存で在り続ける人間は、
絶えず行動の選択を強いられる。」
(サルトル)
実際人間は「何かから自由になる」のではなく、「もともと自由である以外に選択の余地は与えられていない」のです。例えば、目の前に紙と鉛筆を出されて“自由にすればいい”と言われたらどうするか。私達はその紙と鉛筆をどうしようとも“自由”なのです。描いても描かなくても、破っても、折っても、捨てても、無視しても“自由”です。(ここで言う“紙”と”鉛筆“を、“生命”と“人生”に置き換えてみて下さい。)
そう、“自由”とは、全てのことを自分で選択していかなければならないという束縛…“不自由”なのです。だから、「何かをしなければ、何にもなれない」という不自由を常に背負って人間は生きているのです。
頭がよくても使わなければ、お金持ちだったとしても、堕落し何もしなければ何も充実しないのですし、カルト宗教やインチキ占いにのめり込んでしまう人は、権威に依存すれば責任の所在は自分以外になるので安心だと、自己放棄・「誰かに自分の人生を決めてほしい」という選択をしているのです。だから、不幸になりたいと思っても、不幸になる行動を“選択”しなければなりません。
大切なことは、どれだけ虐(しいた)げられた状態に貶(おとし)められたとしても、心がそれにどう応えるか? 自分で選択をしていくことを恐れないこと。その人の一瞬一瞬の行動そのものが、その人の価値観や人間性を自ら決定していきます。つまり、絶望の深淵(しんえん)にたたずんでそれを認めてしまえば、不自由であることを肯定できるのです。生きなければ、死ぬことができない…「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」のです。死んだように生きている人間が、絶望や死ぬことを考えるはずがないのです。
人間は死に向かって生きている…そのどうしようもない喪失感…どうしようもない絶望は、最後に肯定性を持って“孤独”というカタチで社会という鏡に映すようです。
参:孤独とは、閉ざされたものではなく、むしろ社会的広がりのある生き方だ 岡本太郎
「地獄変の屏風(びょうぶ)を描こうとすれば、地獄を見なければなるまいな」 芥川龍之介「地獄変」
一つの能力を獲得するという歓びは、別のある能力を喪失するという哀しみ 茂木健一郎
運というものは、自分をどこに“運ぶ”のか?ということだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このカテゴリーの記事一覧⇒ 人生のヒント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼ブログランキングに参加しています。クリックで応援していただけると励みになります。

Posted by ayanpa at 22:11│Comments(2)
│人生のヒント
この記事へのコメント
まるまるの自由を与えられたら、強い精神力を持っていないと、自由の海におぼれてしまう気がします。
凡人にはそこそこの不自由は必要かもしれません。
凡人にはそこそこの不自由は必要かもしれません。
Posted by 空凛 at 2006年08月12日 13:31
そうですね、「神」の存在意義ってもしかしたらそこにあるのかもしれませんね。
何をしても”自由”だと、逆に何をしていいかわからなくなってしまいますよね。
私の場合、いきなり妻が子供と帰省したりすると、一人の時間をどう過ごせばいいかわからなくなる時があります…。
自由であるのがいいのではなくて、不自由である状況をどう生きるかが大切なのだと私も思います。
何をしても”自由”だと、逆に何をしていいかわからなくなってしまいますよね。
私の場合、いきなり妻が子供と帰省したりすると、一人の時間をどう過ごせばいいかわからなくなる時があります…。
自由であるのがいいのではなくて、不自由である状況をどう生きるかが大切なのだと私も思います。
Posted by ayanpa at 2006年08月13日 22:18
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。